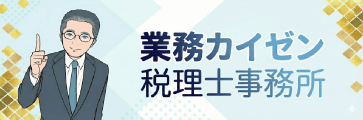2024/12/12〜12/15の日程で、三宅島へ行ってきました。
前回訪島時の記事はこちら。

今回は、いつも行っている税務支援の後に、仲間の土地家屋調査士とタッグを組んで、三宅島の管理不全土地の現況調査を行いました。
私たち「相続土地なんでも相談所」は、土地家屋調査士・司法書士・税理士の専門家チームとして、特に「相続土地国庫帰属制度」の活用を通じて、三宅島をはじめとする東京島嶼部の所有者不明土地問題の解決に取り組んでいます。
今、日本では、
- 所有者がはっきりしない土地(所有者不明土地)
- 管理が全く行われず放棄されている土地(管理不全土地)
が増え、社会問題となっています。
このままでは、近い将来、日本の大切な国土が適切に管理できなくなってしまいます。
「今ならまだ、救える土地があるかもしれない」そんな思いから、今後も定期的に三宅島をはじめとする東京島嶼部を訪れ、調査・支援を行っていく予定です。
管理不全土地の問題
近年、日本では管理不全土地が増加し、大きな社会問題となっています。
管理不全土地とは、所有者の高齢化、相続放棄、不在地主化などにより、適切な管理がなされずに放置されている土地のことを指します。
人口減少や高齢化が進む中、管理不全土地は全国的に増加傾向にあり、不法投棄や災害リスクの増大など、様々な問題を引き起こしています。
こうした管理不全土地の増加に歯止めをかけるべく、国は「相続土地国庫帰属制度」「所有者不明土地あ管理制度」「管理不全土地管理制度」という制度を創設しました。
また、相続登記の義務化については、上に貼った2024年4月の訪島時の記事をご参照ください。
本記事では、今回調査を行った三宅島をモデルケースに、これらの制度の概要と今後の展望について考えていきます。
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈により取得した土地について、所有者からの申請により、その土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。これにより、土地を手放したくても引き取り手がいない地権者の負担を軽減し、管理不全土地の発生を防ぐことが期待されています。
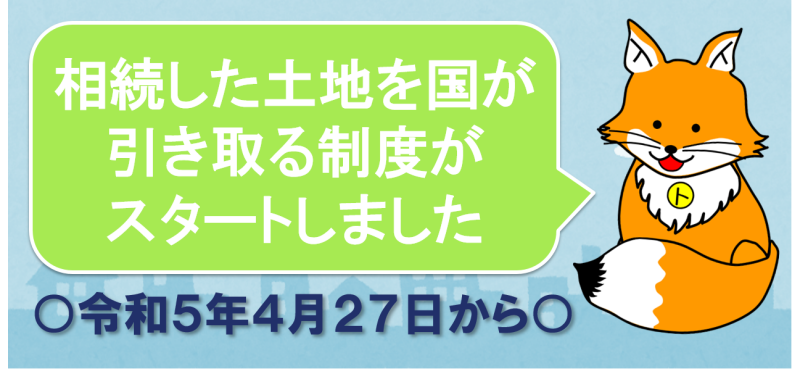
相続土地国庫帰属制度の適用要件
適用対象となる土地は、主に以下のような要件を満たす必要があります。
- 相続や遺贈により取得した土地であること
- 土地の上に建物などが存在しないこと
- 担保権や借地権等の権利が設定されていない土地であること
- 他人による使用が予定されている土地ではないこと
- 境界が明らかでない土地でないこと
条件が厳しいと思われがちですが、実際にはそうでもなく、山林原野なども一概に除外されるわけでもありません。ただ、将来的に法改正で条件が厳しくなる可能性はあると思います。
上記の要件のうち、一番大変な作業が、土地境界を明らかにすることです。
土地境界を明らかにするには、次のような方法があります。

- 自身が認識している境界点に杭や目印を設置し、その写真を撮影する
- 現地に国や地方公共団体が設置した境界標や境界杭がある場合は、それらの写真を撮影する
いずれにしても、現地に行って現況を調査する必要があります。
島の制度適用のサポートをしています
行ったこともなく、どこにあるのかも知らない土地を相続した場合、その場所を特定し、現況を調査し、法務局に提出する資料を作成することは、相続人にとって大変な作業になります。
我々のチームは、土地の専門家である土地家屋調査士をはじめとした士業で構成されています。三宅島をはじめとする東京島嶼部に定期的に通っているため、島での場所特定から現地調査、法的要件の検討などをサポートすることが可能です。
今回も、ある地権者さんからの依頼を受け、現地調査を行っています。現地作業の様子をYouTube動画にしました。
土地家屋調査士 石井さんのHPはこちら
所有者不明土地管理制度・管理不全土地管理制度とは
上記の動画でも少し触れていますが、管理制度も新設(改正)されています。
これは、所有者不明土地および管理不全土地について、裁判所が選任した管理人が管理や処分を行う制度です。これにより、土地の適正な管理や有効活用を促進することが期待されています。
管理人は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士など、一定の資格を持つ者の中から選任され、次のような業務を行うことができるようになります。
- 土地の管理状況の調査
- 土地の管理や処分に関する計画の作成
- 土地の管理や処分の実施
日本は自然災害が頻発する国です。相続土地国庫帰属制度が適用できない場合でも、管理不全土地に管理人をつけて、適切に管理することで、来たるべき災害に備えることが、とても大切だと思います。
三宅島における管理不全土地の実態

三宅島は、管理不全土地問題が深刻化しやすい、次のような特徴を持っています。
- 火山活動
三宅島は活発な火山活動を続ける島であり、1983年と2000年には大規模な噴火により全島民が避難を余儀なくされました。火山活動は、土地の管理や利用に大きな影響を与えています。 - 高齢化・人口減少の進行
三宅島は5人に2人が65歳以上という超高齢化社会です。また、人口減少も進んでいます。この少子高齢化に伴い、土地の管理が困難になるケースが増加しています。特に、島外に移住した若い世代にとって、三宅島にある土地の管理を行うことが難しい、という問題があります。 - 度重なる災害の影響
三宅島は、火山災害だけでなく、台風災害や土砂災害なども発生しています。これらの災害により、土地の荒廃が進んでいる地域も見られます。 - 経済的な制約
三宅島の主要産業は観光業・水産業・農業ですが、経済的に厳しい状況が続いていて、土地の管理に十分な資金を投じることが難しい状況です。 - 相続問題
三宅島では、高度経済成長期の宅地開発計画により分筆され、宅地開発されることなく放置された小規模な土地が多数存在します。これらの土地は、代を重ねるごとに相続人が増え、複雑化し、所有者の特定が年々難しくなっています。相続人の中には島外在住者も多く、それも管理不全土地の発生につながっています。
火山という特殊事情を抱える三宅島において、管理不全土地問題への対策は喫緊の課題だと思います。
三宅島の人はとても親切で、滞在していて、すごく居心地のいい島です。
訪れたことがないかたは、ぜひ一度観光にお越しください。おすすめです。
おわりに
我々は、こうした状況に危機感を抱いており、「今ならまだ間に合い、救える土地があるかもしれない」という思いから、定期的に三宅島を訪れ、相続土地国庫帰属制度等の制度活用を視野に入れた、地権者への情報提供や申請支援などを行っています。
現地に根ざした地道な活動を、これからも続けていくつもりです。
一つ一つの土地を大切にし、次の世代に引き継いでいく。そのために、できることから始めていきたいと考えています。