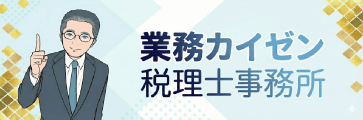私は元システムエンジニアで、現在は税理士として活動しています。
ChatGPTがリリースされた初期の段階から継続的にAIを研究・活用していましたが、Claude Codeが出てきて「これだ!」と飛びついて、現在はClaude CodeとVS Codeを組み合わせた統合開発環境で業務の効率化と高度化を進めています。
従来、AIといえばプログラムコードの生成に注目が集まりがちでしたが、AIの活用範囲はそこだけに留まらず、ビジネスのワークフローを一部代替することができると考えています。
この記事は、Claude Code + VS Code環境の実践的な活用方法について、現時点の私の状況を、具体例を交えて書きました。なお、技術的な事は、日進月歩で情報がどんどん古くなるため、書いていません。
AIは自然言語を理解することができるため、「AIに共通指示書を与えれば、それに従って必要な処理を自律的に行ってくれるようになるのでは?」というのが発想の原点です。法人が新入社員に業務マニュアルを渡すのと同じような感じでしょうか。
- Claude Code
-
Anthropicが開発した、開発者がターミナルから直接AIアシスタント(Claude)にコーディング作業を依頼できるツールです。
- VS Code(Visual Studio Code)
-
Microsoftが開発した無料のオープンソースコードエディタで、多言語対応、拡張機能、デバッグ機能などを備えた軽量で高性能な開発環境です。
AIの本質的価値は「品質の安定化」にある
よく「AIが税理士の仕事を奪う」という議論がありますが、これは本質を見誤っていると思います。AIの真の価値は、職の代替ではなく、業務品質の安定化と高度化にあると思っています。
重要なのは以下の3点です。
- 品質の一貫性:クオリティを均質化する
- 網羅性の確保:漏れを減らす
- 最新情報の反映:情報を更新する
特に3.は、Perplexityが先鞭をつけた、AI自身による自律的なネット検索機能が大きいですね。
Claude Code + VS Code 具体的な活用事例
事例1:文書管理の自動化と高度化
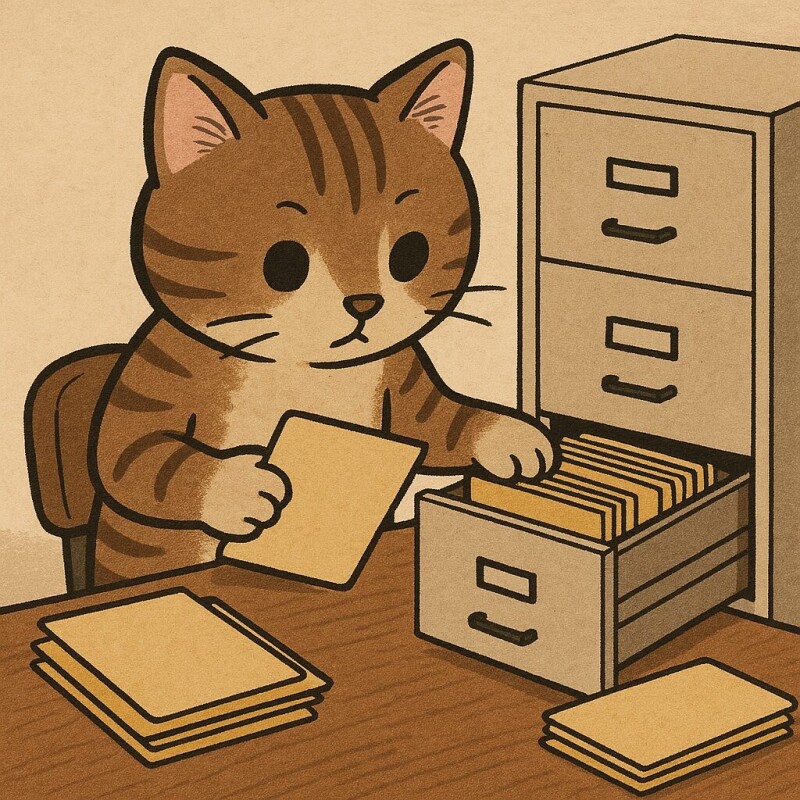
私が携わっている、あるプロジェクトで、メンバーと共有しているフォルダがあり、メンバーがそれぞれ適当に保存して散在していた数百のファイルを、Claude Code + VS Code環境で整理・分類し、フォルダ分けして管理リストを作成しました。
実装内容:
- VS Code上でClaude Codeにファイル分類を指示
- Pythonスクリプトを生成
- 実行・検証・修正
- ファイル内容の自動読み取りと分類ルールの構築
- 関連性分析による横断的なファイル整理
VS Code環境の優位性:
- コード生成から実行までの一連の流れを単一環境で完結
- デバッグとエラー修正をAIと対話的に実施
- 生成されたスクリプトの再利用とカスタマイズが容易
こういった、手作業でやりたくない大量処理系の作業は、AIと相性がいいです。
事例2:専門知識の顧客向けカスタマイズ

税理士向けセミナーの内容を、一般の人でも理解できる形に再構成し、資料を作成しました。
実装内容:
- セミナー録音データの文字起こしと要点抽出
- セミナー配布資料の読み込み・分析
- 録音と資料を総合して論旨を理解
- 専門用語の平易化
- 国税庁の資料と照合し正確性を担保
こうした、「IF(もしこうだった場合)」、今回のケースは「聞き手が税理士ではなく一般の人だった場合」、もAIが得意とする分野だと思います。
Claude Code単体では難しい作業は、Google AI StudioやChatGPTを使って下処理してからClaude Codeに突っ込んでいます。
Claude Code + VS Codeの環境について
技術的な事を書いても、あっという間に陳腐化するので、ここでは考え方だけまとめておきます。
1. 共通指示書による品質管理
システム開発で作成する仕様書の発想で、指示書をVS Codeのワークスペース内で管理しています。AIが作業を実行する際は、まずこの指示書で原理原則を叩き込んでから実行させるようにしています。
意図した出力にならなかった場合に、出力について再指示するのではなく、指示書を都度更新することで対応しています。これにより、同じ指示を何度も繰り返す必要がなくなり、品質の一貫性を確保しています。
指示書は、普通に日本語(自然言語)のマークダウン形式で書いています。
実際の環境では、複数階層に分かれた多少複雑な構成の指示書になっていますが、基本的な考え方は「プロジェクトに共通する指示はファイルに書いておいて、まずそれをAIに読み込ませてから作業をさせる」です。
指示書の構成要素:
- 業務方針とスタイルガイド
- 出力フォーマットの統一基準
- 顧客対応時のルール
- 表記の統一規則
- 禁止事項
など
なお、指示書自体もAIに生成させています。
2. 用語集による表記統一
税務・会計分野特有の表記揺れ問題を、体系的な用語集で解決しています。
用語集の効果:
- 表記を統一
- 顧客向け資料の品質向上
これは、税理士同士でワイガヤ雑談した時の録音データをAIに突っ込んで、頻出単語から用語集を生成させたものをベースにしました。
「税理士は飲み会でも税金の話しかしない」というのは、昔からよく言われてきたようです(笑)
3. 作業ログによる作業蓄積
AIの思考と判断をログに記録させるようにしています。
ログ管理のメリット:
- 過去の判断根拠の確認
- 継続的な改善のためのデータ蓄積
- 作業の中断・再開
作業ログを取ることにより、任意の時点での作業中断・再開が行えるようになっています。
AI時代の業務の未来像
少し前から、政府がDXを唱えて、日本の非効率な業務のやり方自体を変えようとしていましたが、決め手となるブレイクスルー技術が無く、「DX」というフレーズが、ハード・ソフトベンダーの宣伝文句として使われるだけになりつつあります。
AIが、この壁を突破する技術になるのではないか、という気がしています。
やり方が「変わる」のではなく「要らなくなる」ことで、結果的にDX化が進むことを期待しています。
税理士の役割の再定義
冒頭で書いた、「AIで税理士が不要になる」のは、不要になるのではなく、AIを活用できない税理士が淘汰されるだけだと考えています。
私は、業務にClaude Code + VS Codeの環境を使い始めてから、ますます「いままで提供してきた価値とは全く違う、AI時代の付加価値を作り出さなければ」という焦りを感じています。
まだ、何がその価値なのか見い出せていませんが、悩み続けながら進んでいくしか無いと考えています。
ワークフローの根本的変革
私は、税理士以外にも複数のプロジェクトに携わっていて、それぞれについて別のClaude Codeの環境を作って活用しています。
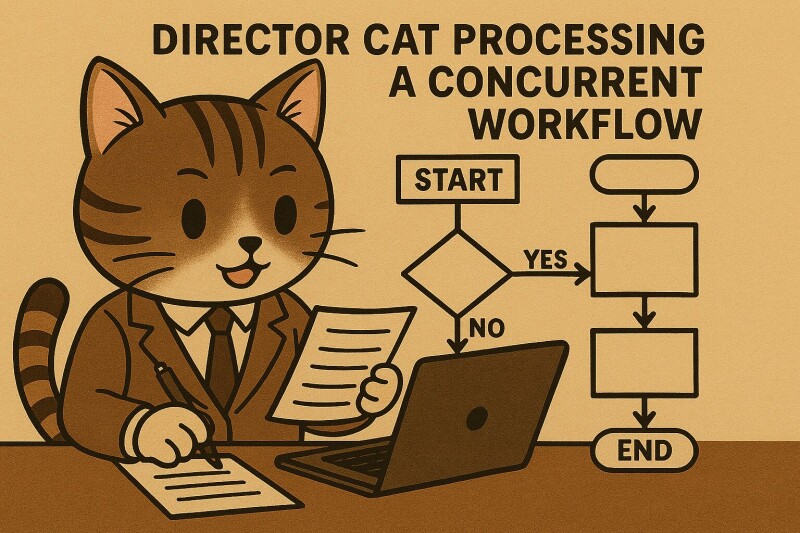
AIの活用により、ワークフローは「順次処理型」から「AIとの対話を通じた同時進行型の作業」に変わっていくと考えています。
- 従来のアプローチ:
-
人間は、直接作業を実行(ポチポチ入力・コツコツ作成)する作業者
- 新しいアプローチ:
-
人間は、AIに指示を出し、品質を管理するディレクターへ
フィードバックループを含んだAI活用のワークフローにより、ワークフロー自体も高度化していきます。
まとめ
私は、インターネットが普及し始めた時の熱気を、今のAIから感じています。インターネットが普及し始めた頃は、タイル状のアポロロケット打ち上げ動画がパラパラと更新されるだけで感動していました。
いま、Claude Codeの環境構築を行い、思った通りの動作をしている、この面白さ・興奮をお伝えしたいと思い、この記事を書きました。

私はスター・トレックはTNGから入ったのですが、TNGで胸のバッチをタップして「コンピュータ、◯◯を△△」と指示しているシーンを、まさに自分がやっている気分です。ワクワクしますね。
※ちなみに、本記事も、本記事内で解説した環境を使い、AIと壁打ちをしながら書いています。タイトルや箇条書きの後ろに「:」をつけたがるのは、Claudeのクセです。